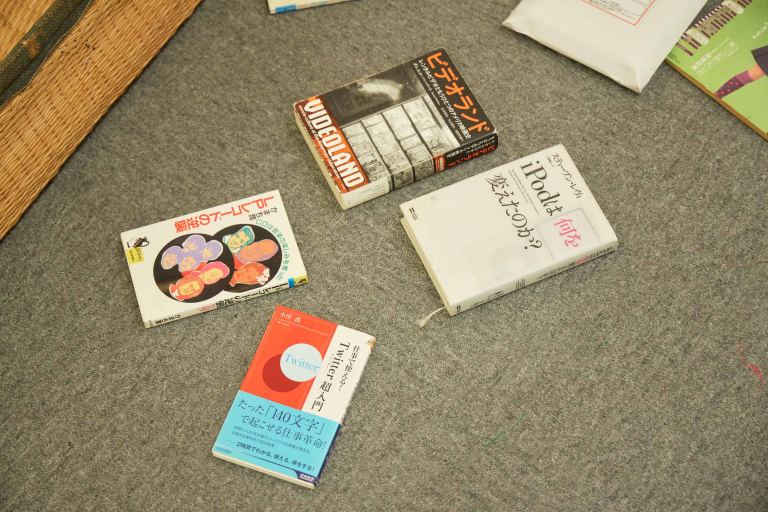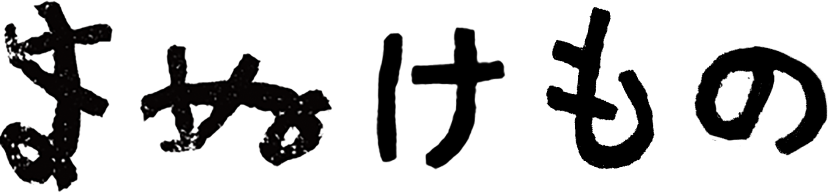
vol.14

その人の持っている“もの”についての話を聞きながら、“まぬけ”の意味を探っていくこの連載。今回登場いただくのは作家の岸田奈美さんです。岸田さんの波乱万丈・トラブルつづきの毎日をつづったエッセイは、軽妙に笑えて、そして「誰も傷つけない」やさしさに満ちていて、日々たくさんの読者が楽しみにしています。そんな岸田さんの身近な「もの」もまた、個性抜群。愛用のスライムを手にしながら、「まぬけもの」を紹介してもらいました。

岸田 奈美 きしだ なみ
大学在学中に創業メンバーとして加入したベンチャー企業で10年間広報部長を務めたのち、休職中に始めたブログが話題となり作家に転身。「キナリ★マガジン」と称したnoteのオリジナル購読サイトで毎月4本新作を更新するほか、『小説現代(講談社)』や『ほぼ日』などでも連載中。2020年に発売したデビュー著書『家族だから愛したんじゃなくて、愛したのが家族だった』(小学館)は、NHKでドラマ化も果たす。そのほか著書に『傘のさし方がわからない』(小学館)、『飽きっぽいから、愛っぽい』(講談社)など。この2月に『もうあかんわ日記』が小学館より文庫化した。
まぬけな自分を救うのは、笑いと便利グッズ

「ひやああ〜ぁ、漏れてるうぅ」
名刺交換を終え、開口一番にこの嘆き。取材のために持ってきてくれたスライムが、カバンの中で容器から漏れていたのだ。
「私、いつもこうなんですよ。ものは落とすし忘れるし、壊すこともしょっちゅう。作家になる前に10年続けた会社員時代なんて、水をこぼしてパソコン4台ダメにしました」
こう話す岸田奈美さんは、主にnoteで執筆をしている作家。ダウン症の弟と、大病の後遺症で車いす生活となった母親を持ち、一筋縄ではいかない家族との日常を綴った話が多くの人の心を掴んでいるが、ご本人は人並みならぬおっちょこちょいらしく、自他ともに認める“まぬけ人間”だそう。
「同じ失敗をしないために、頑張ってはみたんですよ。でも、忘れないようにメモした付箋をなくすし、こぼさないように水を飲まないと決めても、喉が乾けばまた飲んで、またこぼす。30代までは『自分あかんわ』『恥ずかしいわ』と毎度のように自己嫌悪に陥りましたが、休職中に始めたブログで、自分のポンコツさを楽しく読んでくれる人がいると気づいて。まぬけが価値になるんだ、と。それ以降、できないところは無理に変えずに、『私、こんなんやねん!』とありのままで生きられるようになりましたね」
失敗をしないように予防線をはるのも一つの処世術だけれど、岸田さんの場合は「失敗をおもろく書いて、笑ってもらうのが生存戦略」。神戸市出身だから、パンチの効いた関西弁もユーモアを倍増させる。とはいえ、なんとか工夫をできそうなところは、“もの”に頼る。

「手をほったらかしておくと何か倒すし、2つのことを同時にしないと気が散るとわかってから、スライムやスイッチといった手を動かせるものを触っています。読書中や打ち合わせ中も、手元でグニョグニョカチカチ。もちろん相手に断りを入れて。スイッチは、ガチャポンの玩具とか、蚤の市とかで見つけて買うんですよ。それとペンの蓋も、秒でなくすのでプッシュタイプだけにしたり、自分に合った便利グッズに助けられています」

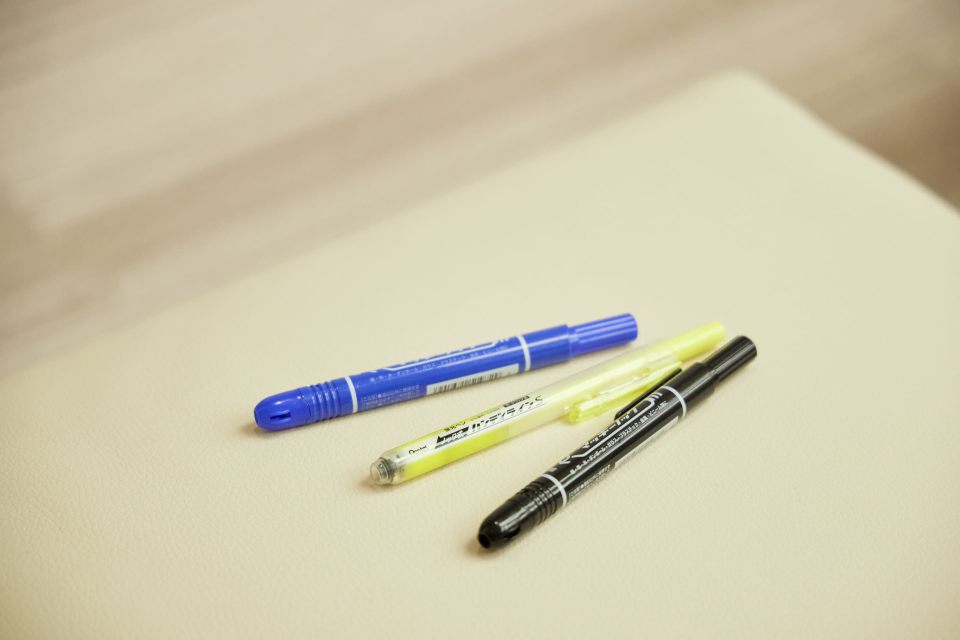

スライムを触らせていただくと、ひんやり冷たくて、ぐにょぐにょとやわらかく、無心で触ってしまう感覚がたしかにわかる。岸田さんは「スライム屋さんになりたい」というほどのスライム好きで、毎月買い足して、今持っているのは50個近く。近年は韓国やアメリカのスライムメーカーが多いらしく、ラメや花の香りがついているものから、なんとトーストのかたちのスクイーズに乗せて楽しめる「フレンチトースト型」までレパートリーも豊富。
「まあでも、スライム自体をカバンに撒き散らしたりもするわけで、失敗はなくならないんですよねえ。しかも、なぜか私は、一生に一度経験するかしないかの大きな災難が、一年に一度のペースで降りかかってくるんです。こないだも、住んでいるマンションの上階の屋根が崩れ落ちてきたし。
だからその分、トラブルへの対処スピードがとんでもなく速くなりました。ものをなくしても各所の落とし物センターの電話番号を覚えてるし、何日間で手元に戻ってくるかも予想がつくし、落ち込んでも1週間後には悲しくなくなる自分自身も知ってる。人生の予習を先にして、瞬発力と馬力を手に入れているわけです」
赤べこは、ダメな自分に寄り添ってくれる
絶対的ヒーロー

ダメな自分を受け入れてくれる「赤べこ」との出会いも、岸田さんを支えている。
「会社員時代、ベンチャー企業だったので、最初は奇抜なアイデアや行動力が評価されていたんですけど、社員が多くなると『みんなと同じことができる』のが前提になる。なので、当たり前ができない自分は怒られることも増え、他者評価の低さに自信も尽きた。そんなとき、出張先で見つけたのが赤べこでした。うんうん頷いて、『大丈夫やで』『合ってるで』って全肯定してくれる姿に励まされたんです」

それから、白黒のモノクロべこや虹色のカラーべこなど10匹ほどを仕事机に並べて、悲しいことがあればペコペコしてもらうように。ただ、頷かせすぎて首がバカになってきているらしく、なんなら横に振り始めている子も。「人生の頷き回数を突破しちゃった」と岸田さん。
2019年に岸田さんがnoteで綴った、『弟が万引きを疑われ、そして母は赤べこになった』というエピソードの中でも、タイトルどおり赤べこが登場する。コンビニのオーナーが、岸田さんの弟にツケでジュースを買わせてあげたのだが、万引きしたと思ったお母さんが「すいません、すいません」と頭を下げている姿が赤べこみたいだった、という話。岸田さんのデビュー著書『家族だから愛したんじゃなくて、愛したのが家族だった』がNHKでドラマ化した際にも象徴的に描かれたため、お母さんが「赤べこの人」と呼ばれることもあるのだそう。

「ドラマといえば、現場でいただいたものも大切にしています。弟役を演じてくれた吉田葵くんがハンカチをくれたのですが、母には可愛らしい桃柄、弟にはクールな車柄を渡してくれたなか、私はなぜかお相撲柄(笑)。『なみちゃんに、絶対ぴったりなのを、みつけましたー!』って。理由は聞けなかったけど、人生どっこい大丈夫感があるのかしら。

あと、私の役を演じてくださった河合優実さんも、『たまたまお店で見つけて、ゼッタイ奈美さんだと思って!』と同じノリで渡してくれたのが、この整理整頓袋。……これも理由は聞けなかったけど、整理整頓できてないように見えるんだろうなあ(笑)」
父の妙なこだわりが残した、人生のメッセージ

話は変わって、今日着ている洋服のこと。ここにも、岸田さんならではの思いが。
「ズボラなので、服も汚してすぐ着れなくしちゃう。じゃあたくさん買ってみても、トレンドはすぐ過ぎ去ってしまう。服って難しいねえ、とヘラルボニーの松田文登さんに話していたら、仕事用の制服を作ってくださって。障がいを抱えている作家さんの作品もアートとして素晴らしくて、誰かに頼まれずとも描き続ける、屈託のない姿勢が好きですね」

ハンカチや名刺入れもヘラルボニー。利便性や社会的に格好いいとされるかどうかではなく、岸田さんの基準は常に“自分が好きと思えるかどうか”。そのこだわりのDNAは、今は亡き父親から引き継がれているのだという。

「おとんは、常に時代の二歩先をいく人でした。外国に目を向けて、『こんなの誰も持ってない!カッコええぞ!』ってものを見つけてくるのが大好きで。小学生の頃は、デンマークから船便で個人輸入した、滑り台付きの勉強机を買い与えられ、休日には、大学やアメリカをイメージした洋風建築が並ぶ住宅街に連れ回されて建築鑑賞。それこそログハウスにも強い憧れがあったので、神戸にあるBESSの展示場にも何度も足を運びましたよ。
初めて観せてくれた映画は、クリント・イーストウッドの『スペース カウボーイ』。おじさんだけでロマンをもって月に行く話。今でこそ貴重な経験だったと思いますが、当時は、普通にドラえもん見せてやって思ってましたね(笑)」
こんなカルチャー的英才教育の根底には、未来を見据える父親からのメッセージが。
「『ファービー』の人形を買ってくれたのですが、輸入ものの英語バージョンで、ずっとアメリカンジョークを言ってるんです。なんでなんって聞くと、『これからはグローバルやから、英語喋れるやつが勝つねん』って。幼稚園児の頃にiMac G3をプレゼントしてくれたんですが、小学生になって友達ができなくて泣いていたら、『お前の友達は、この箱の向こうになんぼでもおるからな、これで友達作れ』って。村上龍の『13歳のハローワーク』をくれた時も、この中からなりたい職業を選べってことなのかと思いきや、『アホか、お前が大人になる頃にはロボットに仕事を取られてるから、この中にない仕事を作れ』と」
学校で教わることの何倍も、核心をついた教えである。岸田さんが独自の道を歩む理由が、垣間見える気がする。そんな父親の背中を追って、岸田さんは最近シブい車を手に入れたのだそう。

「おとんはボルボ940に乗ってたのですが、ドラマではボルボ240エステートが使用されて。撮影後は払い下げになると聞いたので、おとんを思い出して『欲しいです!』って言ったらなんと持ち主の方から譲っていただいて。だけど、メンテナンスにお金はかかるわ、フロントガラスは割れるわ、トランクは外れるわで、手がかかりすぎる!(笑)」
でも、それこそが愛おしさだと岸田さん。「自分がダメだからかもしれないですが、手がかかるって可愛いんですよ。それを持てる自分は、まだ誰かや何かへ優しくできる心が残っているのだなと安心もしますしね」
まぬけとは、人を油断させられること

最後、やはり欠かさず聞いてみたいことは、岸田さんの文章について。母親の入院と大手術、祖父の他界、祖母の認知症が同時多発し、ダウン症の弟の面倒も見ながら岸田さん1人ですべてを担うことになった日々を綴った『もうあかんわ日記』は恐ろしく荷の重い話とは裏腹に、笑いを誘う表現によって、ズンズン読み進められる軽やかさがある。たとえば、祖母の痴呆を「タイムスリップ」と言っていたり。どんな心持ちで書いているのだろうか?
「実際話す時もそうなのですが、私の喋りには間(ま)がない。文章になるとなおさらで、話し相手もいないしnoteに文字数制限もないので、好き勝手書いてギッチギチに埋めてしまうんです。一息つくひまもない感じ。
でも、それを人様に読んでいただくからには、せめて笑顔になってもらいたい。だから、恥もさらして笑いに変えて、“ま”や“ぬけ”にするようにしていますね。おとんもよく、『人を笑かせる人が一番格好ええ。泣かせたり怒らせたりするのは簡単だけど、笑わせるのは一番難しいからな』と言っていたので、その価値観も引き継いでいるなと思いますね」
そして、“まぬけ”は人を油断させられるもの、と岸田さん。
「人間は、自分より弱いものを見たときに油断する。そして、自分の弱さを打ち明けることができて、強がる必要がなくなる。だから、人に舐められるって素敵なことですよ。私の弟はまさにそんな存在で、先ほどのコンビニの話もそう。機械的に働くことで自信をなくしていた店員さんは、『ありがとう』『こんにちは』と大きな声で健気に挨拶をする弟に励まされたそうです。それで、社会的にはよくないけれど、『ツケにする』という優しい気持ちが生まれたのだなと。誰かを思う、非合理的なピュアな気持ちを引き出す力が、まぬけにはあるのだと思います」

Editor’s note
大忙しの岸田さんの毎日をやさしく支える「まぬけもの」たち。「何だろ、これ?」というものから広がる、本人やご家族をとりまくエピソードの数々。穏やかな笑いが絶えない時間はまるで、岸田さんのエッセイを読むときのようでした。そんなエッセイはいくつかの著書となっていますが、インタビューにも登場した『もうあかんわ日記』がつい最近、文庫化しました。紙の本になるときはwebで見るのと読み口が異なるから、紙面を意識して加筆しているそうです。webで読んでいたという方も、まだ岸田さんの本を手にしたことがないという方も、気になったらぜひチェックしてみてください!